業務提携のニュースを発表したいけれど、プレスリリースの書き方がわからずに悩んでいませんか?せっかくの重要な提携なのに、その価値が十分に伝わらないプレスリリースでは、メディアに取り上げてもらえない可能性があります。
業務提携プレスリリースの書き方には、通常のプレスリリースとは異なるポイントがあり、両社の強みや提携の意義を効果的に伝える工夫が必要です。適切な書き方を知ることで、メディアの注目を集め、提携の効果を最大化できます。この記事では、業務提携の価値を最大限に引き出すプレスリリースの基本構成から実践テンプレート、そして配信後の広報戦略まで、初心者でもすぐに活用できるノウハウを具体的な事例とともに解説します。
業務提携プレスリリースの書き方と配信する3つのメリット
業務提携は企業にとって大きな転機となる出来事です。この重要な情報をプレスリリースという形で発信することで、様々なメリットが得られます。
この章では、業務提携のプレスリリースを配信する意義と、それによって得られる3つの主要なメリットについて解説します。自社サービスの認知度を高め、信頼性を向上させる方法や、新たなビジネスチャンス創出の機会、そして企業の成長戦略や将来性をアピールする方法について詳しく見ていきましょう。適切に作成されたプレスリリースは、業務提携の効果を最大限に引き出す強力なツールとなるでしょう。
自社サービスの認知度向上と信頼性アップが図れる理由
業務提携のプレスリリースを配信することで、自社サービスの認知度向上と信頼性アップが実現します。なぜなら、提携先の企業がすでに持つ市場での評判や知名度を活用できるからです。特に自社より規模の大きな企業や、業界で信頼されている企業との提携を発表することで、「あの会社と組んでいる企業」という認識を広められます。例えば、スタートアップ企業が大手企業と提携した場合、その情報がメディアに掲載されれば、一気に注目度が高まるでしょう。
また、「この企業は信頼できる企業から選ばれている」という印象を与えられるため、顧客からの信頼性も向上します。特に新しいサービスを展開する際には、業務提携のプレスリリースが効果的な広告となり、単独での広報活動よりも多くの人の目に触れる可能性が高いといえます。認知度と信頼性の向上は、新規顧客獲得や取引拡大につながる重要な土台になるかもしれません。
新たなビジネスチャンスやステークホルダーとの接点を生み出す効果
業務提携のプレスリリースは、思いがけない形で新たなビジネスチャンスを生み出すきっかけになります。プレスリリースがメディアに掲載されると、その情報は多くの関係者の目に触れます。その中には、あなたの企業と提携してみたいと考える他社の担当者や、投資家、業界のキーパーソンが含まれているかもしれません。実際に多くの企業が、1つの業務提携の発表がきっかけで次々と新たな提携話が持ち込まれた経験を持っています。
また、業務提携のニュースは、取引先や顧客、就職希望者など、様々なステークホルダーにポジティブな印象を与えます。例えば「この会社はどんどん成長している」「新しい分野に挑戦している」といった印象です。
特に就職活動中の学生や転職希望者にとっては、企業の将来性を判断する重要な材料となるでしょう。プレスリリースという一つの情報発信が、予想以上に広範囲な反響を呼び、企業の成長を加速させる可能性を秘めているのです。
企業の成長戦略や将来性を効果的にアピールする方法
業務提携のプレスリリースは、企業の成長戦略や将来性を世の中にアピールする絶好の機会です。提携によって今後どのような事業展開を目指すのか、市場でどのようなポジションを獲得しようとしているのかを明確に伝えることで、企業の方向性を示せます。
例えば「AIベンチャーとの提携により、データ分析技術を強化し、来年度は営業支援ツールの機能を大幅に拡充する計画です」といった形で具体的な展望を示すと説得力が増します。また、業界内での立ち位置を強化する狙いや、新市場への参入意欲なども、提携の文脈で自然に伝えられるでしょう。
特に株式上場を目指す企業にとっては、事業拡大の具体的な動きを示すことで投資家からの評価を高められます。プレスリリースの中で経営トップからのメッセージを盛り込むと、企業の意欲や熱意がより直接的に伝わるかもしれません。業務提携の発表は、単なる事実報告ではなく、企業の未来へのコミットメントを社会に宣言する場なのです。
業務提携プレスリリースの書き方における3つの重要ポイント
業務提携のプレスリリースを作成する際には、ただ提携の事実を伝えるだけでは不十分です。この章では、読み手に強い印象を残し、メディアに取り上げられやすいプレスリリースを書くための3つの重要ポイントを紹介します。
協業の目的や背景をどう伝えるか、両社の強みとシナジー効果をどう表現するか、さらに将来展望や提携への想いをどう盛り込むかなど、具体的な書き方を解説します。これらのポイントを押さえることで、業務提携の価値を最大限に伝えるプレスリリースが作成できるようになります。
協業の目的・背景と実現する価値を明確に伝える方法
業務提携プレスリリースでは、なぜこの提携が必要なのかという目的と背景を明確に伝えることが大切です。
まず、業界の現状や課題から説明し、その解決策として提携に至ったという流れで書くと分かりやすくなります。例えば「高齢化社会において買い物難民が増加する中、当社の配送サービスとA社の商品管理システムを組み合わせることで、より効率的な買い物支援を実現します」といった形です。
また、この提携によって誰にどんな価値をもたらすのかを具体的に示すことが重要でしょう。「利用者は注文から配達まで一貫したサービスを受けられるようになり、配達時間が従来の半分に短縮されます」など、数字を交えた説明があると説得力が増します。背景や目的を説明する際は、社会的な課題解決という大きな視点と、顧客へのメリットという具体的な視点の両方から書くと、提携の意義がより明確になります。読み手に「なるほど、この提携は必要だ」と思わせる内容が、プレスリリースの土台となるのです。
両社の強みとシナジー効果を具体的に説明するテクニック
業務提携のプレスリリースでは、提携する両社がそれぞれどんな強みを持ち、それらを組み合わせるとどんな良いことが起きるのかを具体的に説明することが重要です。
まず、各社の強みを簡潔に紹介します。「A社は全国5万店の小売ネットワークを持ち、B社はAI技術を活用した需要予測システムに強み」といった形です。次に、この組み合わせで生まれるシナジー(相乗効果)を具体的に説明しましょう。「A社の販売データとB社のAI技術を組み合わせることで、各店舗の特性に合わせた最適な在庫管理が実現し、廃棄ロスを30%削減できる見込みです」のように、数字を用いた説明が効果的です。
また、「1+1が2以上になる」具体例として、新サービスの特徴や、既存サービスの進化点を箇条書きで示すと分かりやすいでしょう。重要なのは抽象的な表現を避け、「何がどう良くなるのか」を誰が読んでも理解できる言葉で伝えることです。両社の担当者の声を引用して「A社の○○と当社の△△を組み合わせることで、今までにない価値を提供できる」といった説明を加えると、より生き生きとした内容になるかもしれません。
将来展望と提携への想いを効果的に盛り込む書き方
業務提携プレスリリースの締めくくりとして重要なのが、将来展望と提携への想いです。この提携を通じて両社が目指す未来像を描くことで、読み手に長期的なビジョンを伝えられます。具体的には「2025年までに全国主要都市での展開を目指し、5年以内に市場シェア30%の獲得を目標とします」のように、数字を交えた明確な目標があると説得力が増すでしょう。
また、提携によって解決したい社会課題や実現したい世界についても触れると、提携の意義がより深く伝わります。「高齢者が安心して暮らせる社会の実現に向けて、両社の技術とノウハウを結集します」といった表現です。
さらに、両社の代表や担当役員からの想いを直接引用すると、人間味のある内容になります。「この提携は単なるビジネス上の協力関係ではなく、共通の理念に基づく長期的なパートナーシップです」といったメッセージは、提携の本質を伝えるのに役立つかもしれません。将来展望と想いを伝えることで、この提携が一時的なものではなく、持続的な価値を生み出すものだという印象を与えられるのです。
業務提携プレスリリースの書き方で注意すべき点と避けるべきNG例
業務提携のプレスリリースを作成する際には、陥りがちな失敗やミスに注意する必要があります。適切に情報を伝えないと、せっかくの業務提携の価値が十分に伝わらないばかりか、誤解を招くこともあります。
この章では、業務提携プレスリリスの書き方で特に気をつけるべき点とよくあるNG例を紹介します。主語と責任範囲をはっきりさせる方法、提携先と連携しながら内容を詰める手順、そして視覚的な要素を取り入れる工夫についても解説します。これらのポイントを押さえることで、読み手に正確かつ分かりやすく情報を伝えるプレスリリースが作成できるでしょう。
主語と責任範囲を明確にし読み手を混乱させない表現方法
業務提携のプレスリリースでよくある失敗は、「どちらの会社が何をするのか」が分かりにくいことです。特に両社の役割分担や責任範囲があいまいだと、読み手を混乱させてしまいます。
まず、文章の主語を常に明確にしましょう。「両社は」ではなく「A社は〇〇を提供し、B社は△△を担当します」のように具体的に書くとよいでしょう。また、「連携して取り組みます」といった曖昧な表現よりも「A社はデータ分析技術を、B社は店舗ネットワークを活用し、共同で新サービスを開発します」のように役割を明確にします。
今後のスケジュールについても、「サービス開始は2023年春を予定しています」といった具体的な表現を心がけましょう。責任範囲についても「本サービスの開発はA社が主導し、マーケティングはB社が担当します」のように明記するとよいかもしれません。主語と責任範囲が明確なプレスリリースは、メディアも記事化しやすく、読者も理解しやすいという大きなメリットがあります。
提携先と密に連携しながら内容を正確に伝えるための準備
業務提携のプレスリリースは、必ず提携先と協力して作成する必要があります。片方だけで内容を決めてしまうと、相手側の認識とのズレが生じ、発表後のトラブルにつながりかねません。
まず、プレスリリースの作成スケジュールを両社で共有し、どのような流れで進めるかを決めましょう。特に提携の目的や背景については、両社の認識が一致しているか確認することが大切です。また、お互いの会社概要や製品・サービスの説明は、必ず相手側に確認してもらいます。表現の細かな違いが、意味の取り違えを招くこともあるでしょう。
さらに、発表のタイミングも両社で調整が必要です。「上場企業の場合、適時開示のルールに従う必要がある」といった点にも注意が必要かもしれません。最終的な承認プロセスも明確にし、両社の担当者だけでなく、必要に応じて経営層の確認も取りましょう。密な連携と丁寧な確認作業は、正確で両社が納得できるプレスリリースを作成するための基本といえます。
視覚的要素を効果的に活用し理解度を高める工夫
業務提携のプレスリリースは文字情報だけでなく、視覚的な要素を加えることで理解度が大きく高まります。
両社のロゴを並べて掲載することで、一目で提携関係が分かります。また、提携によって実現するサービスやプロダクトのイメージ図があると、具体的なイメージが湧きやすくなるでしょう。例えば「A社の技術とB社の販路を組み合わせて新市場を開拓」といった関係性を図式化すると、複雑な提携内容も分かりやすくなります。
両社の代表者が握手する写真なども、提携の雰囲気を伝えるのに役立ちます。データや数字を含む場合は、グラフや表を活用すると情報が整理されて伝わりやすくなるかもしれません。ただし、視覚的要素を入れすぎると煩雑になるため2〜3点に絞るのがコツです。適切な視覚要素の活用は、文章だけでは伝わりにくい提携の意義や関係性を直感的に理解させる手助けになります。
業務提携プレスリリースの書き方の成功事例と実践テンプレート
理論を学んだら、次は実践です。この章では、実際に大きな反響を得た業務提携プレスリリースの事例を業種別に分析し、そのポイントを解説します。
また、すぐに使える業務提携プレスリリースのテンプレートと記入例、そしてプレスリリース配信後の効果を最大化するための広報施策についても紹介します。これらの事例とテンプレートを参考にすることで、自社の業務提携をより魅力的に伝えるプレスリリースが作成できるようになるでしょう。
業種別の成功事例分析と参考にすべきポイント
様々な業界の企業が発表した業務提携プレスリリースの中から、特に反響の大きかった事例を見ていきましょう。
IT業界では、クロスマート株式会社のプレスリリースが好例です。彼らは大手クラウドサービスとの連携を発表する際、「両社の技術を組み合わせることで実現する3つの新機能」を具体的に示し、ユーザーメリットを分かりやすく伝えました。
小売業では、キャブステーションの事例が参考になります。宅配サービス企業との提携を発表する際、「買い物難民問題の解決」という社会的意義を前面に出し、地域貢献という視点で話題を集めました。
医療分野では、株式会社ICHIGOの事例が印象的です。医療機器メーカーとの提携発表で、患者さんの声を交えながら医療現場の課題解決に焦点を当てています。
また、テクノロジー企業のRidge-iは、AI技術の製造業への応用を目指す提携で、具体的な導入効果を数値で示し説得力を高めました。これらの成功事例に共通するのは、「提携によって何が変わるのか」を具体的かつ分かりやすく伝えている点です。業界の特性に合わせた切り口で、提携の意義を強調することが大切でしょう。
すぐに活用できる業務提携プレスリリースのテンプレートと記入例
業務提携プレスリリースの作成の手間を省くために、すぐに使えるテンプレートを紹介します。基本的な構成は以下の通りです。
「タイトル(両社名と提携内容を含む)」→「リード文(提携の概要を1〜2段落で)」→「本文(提携の背景・目的、提携の内容、実現すること、役割分担)」→「今後の展開」→「両社からのコメント」→「会社概要」→「問い合わせ先」
タイトルは「○○社と△△社、□□に関する業務提携を開始」といった形式が一般的です。リード文では「○○社と△△社は、本日、□□を目的とした業務提携を開始しました」と簡潔にまとめましょう。本文では両社の強みと提携で実現することを具体的に説明し、役割分担も明記します。コメントは両社の代表や担当役員の言葉を引用し、提携への思いや期待を伝えます。このテンプレートに沿って情報を埋めていけば、プロのような仕上がりになるでしょう。
記入例として「AI開発のA社と販売網を持つB社の提携」のケースを示すと、背景には「AI技術の実用化と販路拡大」、実現することには「AIを活用した需要予測サービスの全国展開」といった具体的な内容を盛り込むとよいかもしれません。
プレスリリース配信後の効果を最大化する広報施策
業務提携のプレスリリース配信はゴールではなく、広報活動のスタート地点です。配信後の効果を最大化するために、いくつかの追加施策を実施しましょう。
まず、両社のウェブサイトやSNSアカウントで提携の発表を共有します。その際、プレスリリースの内容をかみ砕いて、より簡潔に伝えるとよいでしょう。次に、両社の共催でオンラインセミナーやウェビナーを開催するのも効果的です。「提携によって実現する新サービスの詳細説明会」といった形で、より深い情報を提供できます。また、提携に関連する特設サイトやランディングページを作成し、詳細情報や利用方法、導入事例などを掲載するのも良い方法です。
記者向けの説明会を開催したり、業界メディアに個別取材を提案したりすることで、より詳細な情報発信も可能でしょう。さらに、提携後の進捗や成果については定期的にアップデート情報を発信し、継続的な関心を維持することが大切です。プレスリリースは一度きりの情報発信ではなく、長期的な広報戦略の一部として位置づけると、業務提携の効果を最大限に引き出せるかもしれません。
業務提携プレスリリースの書き方まとめ:提携効果を最大化する戦略的活用法
本記事では、業務提携プレスリリースの書き方について詳しく解説してきました。効果的なプレスリリース作成のポイントを振り返りましょう。
- 業務提携のプレスリリースには、認知度向上、新たなビジネスチャンス創出、企業の将来性アピールという3つのメリットがあります
- 協業の目的・背景を明確に伝え、両社の強みとシナジー効果を具体的に説明することが重要です
- 主語と責任範囲を明確にし、提携先と密に連携しながら内容を正確に伝えましょう
- 視覚的要素を効果的に活用し、理解度を高める工夫も大切です
- 成功事例を参考にしつつ、テンプレートを活用して作成すると効率的です
業務提携プレスリリースの書き方を身につければ、単なるお知らせではなく、企業の価値を高める戦略的な広報ツールとなります。今回紹介したテンプレートや事例を参考に、ぜひあなたの企業の業務提携を魅力的に伝えるプレスリリースを作成してみてください。効果的なプレスリリースが、提携の効果を最大限に引き出し、ビジネスの新たな可能性を広げるでしょう。
付録:業務提携プレスリリース フォーマット
業務提携プレスリリースの例です。コピペしてフォーマットとしてお使いください。
【プレスリリース】
[発表日]
[企業A名]
[企業B名]
[企業A名]と[企業B名]が業務提携
〜[提携の目的や内容の簡潔な説明]〜
[企業Aの事業内容]を行う[企業A名](本社:[所在地]、[代表者役職・氏名])と、[企業Bの事業内容]を行う[企業B名](本社:[所在地]、[代表者役職・氏名])は、[発表日]、[提携内容の簡潔な説明]に関する業務提携契約を締結いたしました。
■提携の目的
本提携は、[提携の目的や背景の詳細説明]。
■提携の内容
- [提携内容1]
- [提携内容2]
- [提携内容3]
- [提携内容4]
■今後のスケジュール
[時期1]:[予定内容1]
[時期2]:[予定内容2]
[時期3]:[予定内容3]
[時期4]:[予定内容4]
■両社コメント
[企業A名] [代表者役職] [氏名]
「[企業Aの代表者コメント]」
[企業B名] [代表者役職] [氏名]
「[企業Bの代表者コメント]」
■会社概要
【[企業A名]】
所在地:[住所]
設立:[設立年月]
代表者:[代表者役職・氏名]
事業内容:[事業内容]
【[企業B名]】
所在地:[住所]
設立:[設立年月]
代表者:[代表者役職・氏名]
事業内容:[事業内容]
本件に関するお問い合わせ先
[企業A名] [担当部署] [担当者名]
TEL:[電話番号]
Email:[メールアドレス]

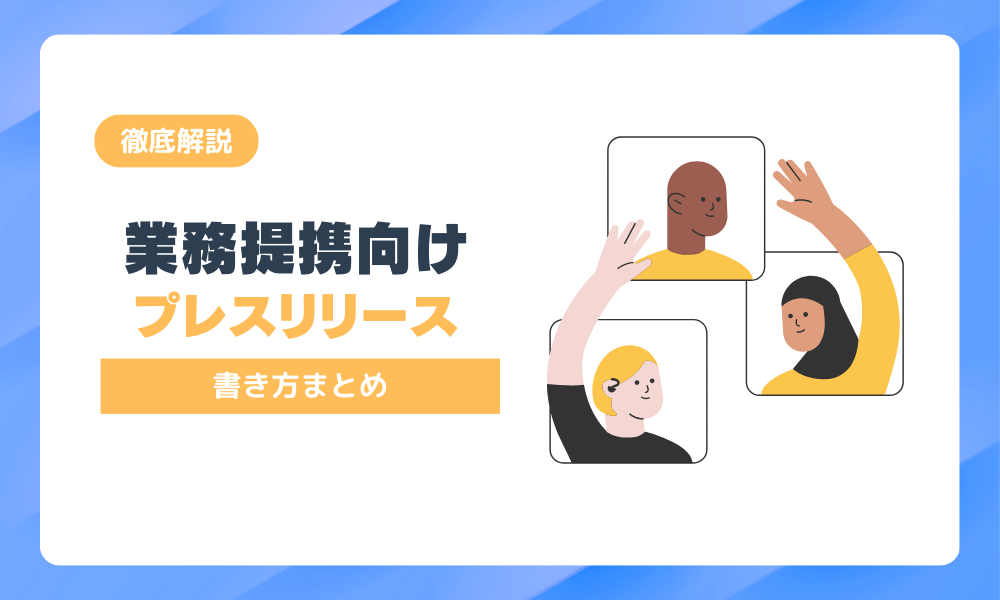

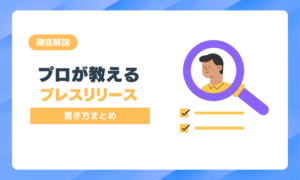


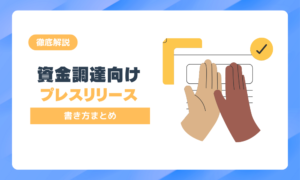

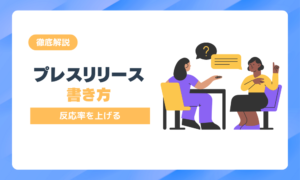
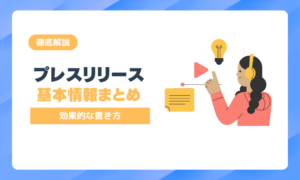
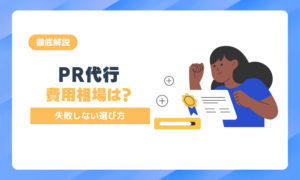
ご不明点があればコメントください!