BtoB プレスリリース 書き方に悩む企業担当者は少なくありません。「せっかく作成しても記者に読んでもらえない」「何を書けば良いのかわからない」「競合他社のプレスリリースの方が取り上げられている」など、効果的な情報発信に苦労されてはいませんか?
企業間取引が中心のBtoB企業こそ、プレスリリースを戦略的に活用することで、業界内での認知度向上や信頼性アップ、さらには新規顧客開拓につなげることができます。適切な書き方を知ることで、メディアに取り上げられる確率が高まり、自社の強みを多くのステークホルダーに伝えられるようになります。
この記事では、BtoB企業特有のプレスリリース作成のポイントから、業界別の成功事例、具体的なテンプレートまで、すぐに実践できる内容を詳しく解説します。これからプレスリリースを作成する方も、効果がイマイチだった方も必見の内容です。
BtoB プレスリリース 書き方の基本とその効果
BtoB企業のプレスリリースは、取引先や業界関係者に自社の最新情報を伝える重要なツールです。この章では、BtoB企業がプレスリリースを活用する基本的な考え方とその効果について解説します。
- プレスリリースがBtoB企業のブランディングや信頼性向上にどう役立つ?
- 顧客企業や投資家、就職希望者など様々な関係者へのプレスリリースの影響力
- 一般消費者向けのプレスリリースとの違いや、BtoB特有の書き方のコツ
BtoB企業のプレスリリースは単なるお知らせではなく、ビジネス拡大のための戦略的なツールといえるでしょう。正しく活用すれば、メディア露出だけでなく、直接的な商談機会の創出にもつながります。特に専門性の高い業界では、プレスリリースが技術力や先進性をアピールする絶好の機会となるかもしれません。
BtoB企業がプレスリリースを活用すべき理由
BtoB企業にとって、プレスリリースは想像以上に大きな価値があります。まず第一に、業界内での認知度向上に直結します。専門メディアに取り上げられることで、潜在顧客である企業担当者の目に留まる確率が高まるでしょう。
また、新サービスや技術開発の発表は、自社の専門性や先進性をアピールする絶好の機会です。特に技術力が重視されるBtoB分野では、こうした情報発信が取引先からの信頼獲得につながります。プレスリリースを通じて専門知識や市場分析を示すことで、業界のオピニオンリーダーとしての地位を確立することも可能です。
さらに、投資家や株主向けの情報発信としても効果的です。事業の進捗や成長性を定期的に発信することで、企業価値の向上にも寄与します。採用活動においても、自社の取り組みや技術力を知ってもらうきっかけとなり、優秀な人材確保にもつながるといえます。
BtoB特有のプレスリリース効果とステークホルダーへの影響
BtoB企業のプレスリリースは、様々なステークホルダーに対して独自の効果をもたらします。まず取引先企業に対しては、自社の安定性や成長性をアピールする材料となります。新規の提携発表や技術開発の成功は、取引先に安心感を与え、長期的な関係構築に役立つでしょう。
投資家や株主に対しては、事業の進捗や市場での評価を伝える重要な手段です。特に上場企業では、IRの一環としてプレスリリースが重視されます。市場動向の分析や業界データを含めたプレスリリースは、投資判断の材料として高く評価されるかもしれません。
また、業界全体に対する影響力も見逃せません。先進的な取り組みや業界課題への提言は、業界内でのポジショニングを確立する機会となります。特に専門メディアでの露出は、業界内での存在感を高め、営業活動をサポートする強力な味方となるでしょう。
BtoBとBtoCプレスリリースの違いと特徴
BtoBのプレスリリースは、BtoC(企業対消費者)向けのものとは内容や表現に大きな違いがあります。BtoBでは専門性の高い内容が求められる一方、一般向けよりも深い情報や具体的なデータを提供する必要があるでしょう。
BtoCが感情や利便性に訴えかけるのに対し、BtoBは合理性や費用対効果、業務改善などの観点が重視されます。「コスト削減率30%」「業務効率化による工数削減」など、ビジネス成果に直結する数値や効果を明確に示すことが大切です。
また、ターゲットとなる読者層も異なります。BtoBのプレスリリースは、業界専門家や企業の経営層・調達担当者を意識した内容構成が必要です。業界の課題や市場動向への理解を示しながら、自社サービスがどのようにそれらの解決に貢献できるかを論理的に説明する点が特徴といえるでしょう。
効果的なBtoB プレスリリース 書き方の3つの重要ポイント
BtoBのプレスリリースを書く際には、いくつかの重要なポイントを押さえることで、読み手に伝わりやすい内容になります。この章では、BtoBプレスリリースを書く際の3つの重要ポイントを解説します。
- 社会的背景や業界の課題と結びつけたストーリー展開の組み立て方
- 専門用語の適切な使い方と市場データを効果的に活用する方法
- 図解やグラフなどを使った視覚的に分かりやすい構成のコツ
BtoBのプレスリリースは、専門性と分かりやすさのバランスが重要です。業界知識を持つ人には深い情報を、一般メディアには分かりやすく伝えるという二面性が求められます。これらのポイントを押さえることで、多くの関係者に価値ある情報として受け止められるプレスリリースが作成できるでしょう。
社会背景とストーリーを効果的に伝える方法
BtoBプレスリリースを魅力的にするポイントの一つが、社会背景とストーリー性です。単に製品やサービスの機能を列挙するだけでなく、「なぜそれが必要なのか」という背景から説明しましょう。
例えば、「働き方改革による業務効率化の必要性が高まる中」「サプライチェーンの不安定化が業界課題となる状況で」など、社会的な文脈や業界の課題に触れることで、読み手の共感を得やすくなります。このアプローチは特に業界メディアの記者の関心を引きやすい特徴があるでしょう。
また、開発の経緯や苦労話など、人間的なストーリーを盛り込むのも効果的です。「顧客企業の現場の声をもとに2年かけて開発」「エンジニア100人体制で難題を突破」といった裏話は、技術的な内容に温かみを加え、記事化されやすくなります。ただし、BtoB向けでは感情的要素よりも事実と論理に基づいた展開が基本となる点は忘れないようにしましょう。
専門用語と市場データを適切に活用するテクニック
BtoBプレスリリースでは、専門用語と市場データの活用が重要です。ただし、バランスを考えた使い方がポイントとなります。専門用語を使うことで業界への理解度を示せますが、過度に使いすぎると一般メディアには伝わりにくくなるかもしれません。
専門用語を使う際は、初出時に簡単な説明を付け加えるのが良い方法です。例えば「SaaS(Software as a Service:クラウド型ソフトウェア提供形態)」のように括弧内で解説を入れると、業界外の人にも理解しやすくなります。
市場データの活用も説得力を高める重要な要素です。「2025年には〇〇市場が前年比150%に拡大(△△調査)」など、信頼できるソースの市場予測を引用することで、客観性と信頼性が増します。ただし、データは最新のものを使い、出典を明記することを忘れないようにしましょう。具体的な数字は記者の目に留まりやすく、記事化の可能性を高める効果もあるといえるでしょう。
視覚的要素を取り入れた分かりやすい構成の作り方
文章だけでは伝わりにくい内容も、視覚的要素を取り入れることで理解が深まります。BtoBプレスリリースでは特に、複雑な仕組みやプロセスを説明する場合に図解やグラフが効果的です。
例えば、システム構成図やワークフロー図、before/after比較などは、言葉で説明するよりも一目で理解できる利点があります。「導入前後で処理時間が1/3に短縮」といった効果を示すグラフは、具体的なイメージを与えることができるでしょう。
また、プレスリリース自体の構成も重要です。長い文章の塊ではなく、見出しや箇条書きを効果的に使うことで読みやすさが向上します。特に重要なポイントは太字にしたり、ボックスで囲んだりして視覚的に目立たせる工夫も有効です。多忙な記者や企業担当者が短時間でも要点を掴めるよう、情報の階層化を意識した構成を心がけましょう。
BtoB プレスリリース 書き方で押さえるべき具体的な内容構成
BtoBプレスリリースを作成する際には、盛り込むべき内容があります。この章では、読み手に響くプレスリリースの中身について具体的に解説します。
- 新商品・サービスの特徴や導入メリットをビジネス視点で伝える方法
- 他社との連携や新技術開発を発表する際の構成の組み立て方
- 調査データや導入実績を活用して信頼感を高める書き方のコツ
BtoBプレスリリースは、ただ情報を伝えるだけでなく、ビジネス価値を明確に示すことが大切です。専門的な内容でも分かりやすく伝え、受け手がその重要性を理解できるような構成を意識しましょう。適切な内容構成は、メディアだけでなく、取引先や業界関係者にも強く印象づける力を持っているといえるでしょう。
商品・サービス情報の効果的な伝え方
BtoB向け商品やサービスのプレスリリースでは、具体的なビジネス価値に焦点を当てることが重要です。一般消費者向けと違い、「どれだけコスト削減につながるか」「業務効率がどう改善されるか」など、導入後の具体的な成果を示す必要があります。
例えば、「導入企業の平均で工数30%削減」「初期投資6か月で回収可能」など、数字を使った具体例が説得力を持ちます。また、想定される使用シーンや導入後のワークフローの変化を具体的に描写すると、読み手がイメージしやすくなるでしょう。
さらに、競合製品との違いを明確に示すことも大切です。「業界初の○○機能を搭載」「従来比20%の処理速度向上」など、差別化ポイントを明示しましょう。ただし、他社の名前を出して直接比較するのではなく、自社製品の優位性を客観的に伝える表現を選ぶことがポイントです。顧客にとっての選ぶ理由が明確になれば、商談につながる可能性も高まります。
企業間連携・技術開発に関する情報の構成方法
企業間の提携や新技術開発を発表するプレスリリースでは、その意義や将来展望を含めた構成が効果的です。単に「〇〇社と提携しました」だけでなく、「なぜ提携したのか」「何を目指すのか」を明確に伝えましょう。
まず、連携の背景となる市場環境や課題から説明すると理解されやすくなります。「クラウド化の進展により高まるセキュリティニーズに応えるため」など、社会的文脈を示すことで意義が伝わりやすくなるでしょう。
また、技術開発の発表では、専門的な内容をかみ砕いて説明することが重要です。図や表を活用し、技術の特徴や革新性を視覚的に示すと良いでしょう。「従来技術では困難だった△△が可能になる」など、ブレークスルーを分かりやすく伝えることで、専門知識のない記者にも興味を持ってもらえるかもしれません。
最後に、連携や開発の今後のロードマップを示すことも忘れないようにしましょう。「2023年第2四半期に実証実験を開始、2024年の実用化を目指す」など、具体的な展望があると読み手の関心を引き付けられます。
調査レポートや実績を活用した信頼性の高め方
BtoB企業のプレスリリースでは、調査データや導入実績を上手に活用することで信頼性が大きく高まります。自社で実施した業界調査や市場動向分析は、専門メディアにとって価値ある情報源となるでしょう。
調査データを紹介する際は、「サンプル数」「調査期間」「調査方法」などを明記し、信頼性を担保することが大切です。また、グラフや図表を用いて視覚的に示すと、記者が記事化する際にそのまま使いやすくなるという利点もあります。
導入実績を紹介する場合は、具体的な成果を数値で示すことが重要です。「A社では導入後3か月で業務効率が25%向上」など、具体例があれば説得力が増します。可能であれば導入企業の担当者コメントも含めると、第三者の声として信頼性が一層高まるでしょう。
ただし、顧客企業の事例を掲載する際は、必ず事前に掲載許可を得ることを忘れないようにしましょう。企業名を伏せた形でも、業種や規模を明示することで、読み手は自社との関連性を判断できます。
成功するBtoB プレスリリース 書き方の事例分析
理論だけでなく実例から学ぶことも大切です。この章では、実際に成功したBtoBプレスリリースの事例を紹介し、その成功要因を分析します。
- IT、製造、サービスなど業界別の成功プレスリリース事例と、その特徴や工夫を解説
- 新製品発表、業務提携、調査結果など、目的別に見る効果的なプレスリリースの具体例を紹介
- プレスリリースの配信タイミングや、SNS・自社サイトとの連携で効果を高める方法を伝授
成功事例を参考にすることで、自社のプレスリリース作成に役立つヒントが見つかるでしょう。他社の良い点を取り入れながら、自社らしさを表現することが理想的です。配信のタイミングや関連施策との連携も、プレスリリースの効果を左右する重要な要素といえます。
業界別・目的別の成功事例10選
成功したBtoBプレスリリースの事例から学べることは多いものです。まず、IT業界の例として、クラウドサービス会社A社の「AI搭載データ分析プラットフォーム」発表では、具体的な導入効果を複数の企業事例と共に紹介し、説得力を高めていました。また、図解を多用して複雑な技術を分かりやすく説明した点も評価されたようです。
製造業では、工作機械メーカーB社の「省エネ型次世代工作機械」の発表が注目を集めました。このプレスリリースでは、環境負荷低減という社会課題と結びつけた構成が特徴で、「CO2排出量30%削減」という具体的な数値と、第三者機関の検証結果を併記したことで信頼性が高まりました。
業務提携の例では、物流企業C社とITベンダーD社の連携発表が印象的です。単なる提携発表ではなく、「物流危機を解決する新たな取り組み」という社会的文脈で伝えた点が多くのメディアに取り上げられました。
調査レポート型では、人材サービス会社E社の「テレワーク導入実態調査」が成功例です。1000社以上の大規模調査データを元に、業界未公開だった具体的な課題と解決策を提示したことで、業界紙だけでなく一般経済メディアでも大きく取り上げられました。
他にも、製品アップデート、イベント開催、アワード受賞、海外展開など、様々な目的別の成功事例があります。共通するのは、「なぜそれが重要か」という社会的背景と、具体的なデータや第三者評価を組み合わせている点でしょう。
配信タイミングと連携施策の最適化方法
プレスリリースの効果を最大化するには、適切な配信タイミングと他の施策との連携が欠かせません。まず配信日時については、火曜から木曜の午前中が最も注目されやすいとされています。月曜は週末の情報整理で忙しく、金曜は週末企画準備で埋まりがちなためです。
また、業界の大きなイベントや展示会に合わせた配信も効果的でしょう。ただし、他社の大型発表が予定されている日は避けるなど、競合するニュースが少ない日を選ぶのも重要なポイントです。
連携施策としては、プレスリリース配信と同時に自社サイトでの詳細情報公開やSNSでの発信を行うことで、相乗効果が期待できます。特にLinkedInなどのビジネス向けSNSでの展開は、BtoB企業にとって効果的な手段といえるでしょう。
さらに、プレスリリース配信後のフォローも忘れてはなりません。配信から2〜3日後に記者へのフォローアップを行い、追加情報の提供や取材のオファーをすることで、記事化率が高まることもあります。メディアに掲載された記事は、自社サイトやSNSで改めて紹介し、より多くの関係者の目に触れるよう工夫しましょう。
こうしたタイミングの最適化と連携施策の組み合わせにより、一度のプレスリリースから最大限の効果を引き出すことが可能になります。
BtoB プレスリリース 書き方のよくある質問とチェックリスト
本記事では、BtoB プレスリリース 書き方の基本から応用まで詳しく解説してきました。最後に重要なポイントをまとめます。
- BtoBプレスリリースは単なるお知らせではなく、企業価値を高める戦略的ツール
- 社会背景やストーリーを含め、専門性と分かりやすさのバランスが重要
- 具体的な数値や第三者評価を取り入れることで信頼性が向上する
- 視覚的要素を効果的に活用し、複雑な情報も理解しやすく伝える
- 配信タイミングとSNSなどの連携施策が効果を最大化する
これらの要点を押さえたプレスリリースは、メディアに取り上げられる可能性が高まるだけでなく、取引先や業界関係者に対する強力なコミュニケーションツールとして機能します。
まずは自社の最新ニュースを題材に、今回紹介したポイントを1つずつ実践してみてください。継続的なプレスリリース配信が、あなたの会社のブランド価値向上と事業拡大につながるでしょう。
付録:BtoBプレスリリース フォーマット
BtoBプレスリリースの例です。コピペしてフォーマットとしてお使いください。
【プレスリリース】
[発表日]
[会社名]
[対象業界]向け[製品・サービスカテゴリ]
「[製品・サービス名]」を提供開始
〜[製品・サービスのキャッチコピー]〜
[会社名](本社:[所在地]、[代表者役職・氏名])は、[対象業界]向け[製品・サービスカテゴリ]「[製品・サービス名]」を本日より提供開始することをお知らせいたします。
■サービス概要
「[製品・サービス名]」は、[対象業界・企業規模]向けに開発された、[製品・サービスの詳細説明]。[主要機能の説明]などを備え、[実現できる価値]を実現します。
■サービス開発の背景
[業界の課題や市場状況]。特に[ターゲット企業]では、[具体的な課題]。当社が[時期]に実施した調査では、[関連するデータ]。
■主な特長
- [特長1]:[詳細説明]
- [特長2]:[詳細説明]
- [特長3]:[詳細説明]
- [特長4]:[詳細説明]
- [特長5]:[詳細説明]
■導入効果
導入企業における[検証方法]では、以下の効果が確認されています。
・[効果指標1]:[数値1]
・[効果指標2]:[数値2]
・[効果指標3]:[数値3]
・[効果指標4]:[数値4]
■料金体系
・初期費用:[金額](税別)〜
・月額利用料:[金額](税別)〜
※[料金に関する補足事項]
■導入サポート
[導入時のサポート内容]。標準で[サポート期間]の[サポート内容]が含まれています。
■パートナー企業
[パートナー企業の種類]として、[パートナー企業数や地域]の[パートナー企業名]と提携し、[連携内容]を進めてまいります。
■会社概要
社名:[会社名]
所在地:[住所]
設立:[設立年月]
代表者:[代表者役職・氏名]
事業内容:[事業内容]
本件に関するお問い合わせ先
[会社名] [担当部署] [担当者名]
TEL:[電話番号]
Email:[メールアドレス]



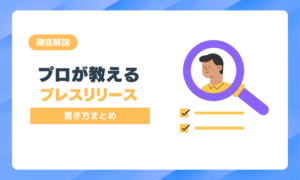

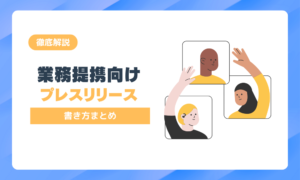
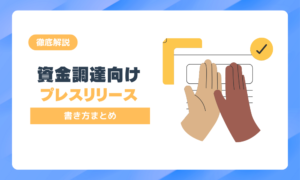

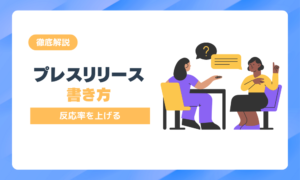
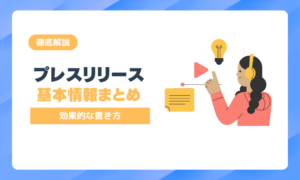
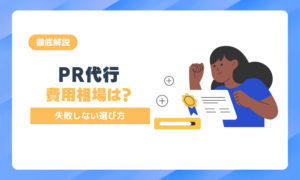
ご不明点があればコメントください!